雑草というものは、農業にとって厄介もの!?。
けれど、昔の農業では雑草を貴重な資源として、農産物の生産に使われてきたのです。
現代の肥料は大変便利になって、とても運びやすく撒きやすくなっています。だたし、ほとんどの肥料は輸入品。しかもやり過ぎによる環境汚染となっている現状を知り、もっと上手に使わないといけないと思っています。

雑草との付き合い方を少しでも楽しくなるようにしたい。
とは言っても除草剤あげましょう。って話ではありません。
どう向き合うか見つめ直してみたい。そう、思いました。
よく、見かける雑草の一つである「ミドリハコベ」をご紹介します。
これは、野菜を作っている畑のわきに生えていた画像です。
「ミドリハコベ」の特徴

「ミドリハコベ」↑その他にも紫色の軸のモノもあって「コハコベ」
「この雑草め~~また生えてきやがった」心の声が思わず…
この雑草は春の七草の一つ「はこべら」こと「ハコベ」ハコベはナデシコ科の一年草です。
秋に発芽して越冬し、春になると可愛い小さな花を咲かせます。
ハウスでは秋口から花をずっと咲かせています。これは春の七草の1つです。
そんな「ミドリハコベ」ですがハウスのほうれん草の周りによく生え、ほうれん草に絡んでしまうと手間がかかって収穫ができません。
チョット厄介もの。その為、今の作業は収穫と除草です。どのように除草しているかと
ほうれん草の除草にはコレ。楽ちん!(^^♪

ほうれん草の間の小さな「ハコベ」が点々と生えてます。とても厄介ですね。
「たがやすパワー」は葉物野菜の除草に便利。

そこで除草する道具、商品名「たがやすパワー」てってて~(^^♪
コロコロ転がすことで、あいだの土を柔らかくし、次の回転刃で草を浮き上げ、すきこみます。ほうれん草が大きくならない本葉2~3枚の頃が一番良い時期です。それ以上にほうれん草の葉っぱ大きくなるとほうれん草の葉が粉々、ハコベもうまく取れません。

ほうれん草を筋にまいた間を「ゴリゴリ」します。

ついでに、土の表面にカビのような青い藻が生えてきたので、土をほぐしてあげます。
これを2回することで完璧。1日に計算すると4㎞コロコロしています。
このように雑草を取り、簡単に土を耕してくれます。10年以上愛用していますが、今でも現役、是非使ってみてください。
「はこべ」について深堀りしましょう。
実は畑の豊かさの象徴とも言える存在が「ハコベ」
①野菜と共生しやすい。 葉物野菜には厄介者ですが、人参と大根とキャベツと仲良く共存しています。抜かなくていい雑草なんです。
混植することで害虫を寄せ付けずよく育ちます。相性の良いコンパニオンプランツなんです。
②他の雑草が生えるのを抑えてくれる 他の雑草が芽を出して、野菜との競い合いになってしまいます。しかし「ハコベ」は背があまり高くならず、根の張りも弱いので、畑の野菜の生育の邪魔になりません。
また「ハコベ」は越冬して春に花を咲かせ、そのあとはタネをつけて枯れていきます。
逆に多くの野菜は春に種まきや苗の植え付けが行われるため、ちょうど成長のタイミングが入れ違いとなります。
野菜の生育に邪魔にならない限りは、できるだけハコベは残しておき、タネをそこに落とさせることで、また翌年もハコベが生えやすい環境になります。
③野菜づくりに適した、土壌環境がでいている一つの目安です。
その他にも、「ホトケノザ」、「オオイヌノフグリ」などがあるんですが、どんな野菜も作れる畑によくある草、つまり「良い畑に生えている」として知られています。つまり「ハコベ」が多い畑はすでにある程度栄養素の量があり、バランスが取れている土である可能性が高いのです。

「ホトケノザ」↑
私のハウスのほうれん草栽培に全く、この雑草の特徴を生かし切れていない。という事です。…
この結果から、雑草は教えてくれている=うまく草を活かせない!と
猛反省(>_<) 分析といい、草といい、「はあ~~(*_*)」ちょっと気分転換に図書館に行ってきました。そこで見つけた書籍が、
先人の草との向き合い方は真逆。
出典:福井県池田町生活編集委員会・福井県南越農業改良普及書s63.3.31
明治初期の農村景観って、ほんと素晴らしいことだったのでしょう。
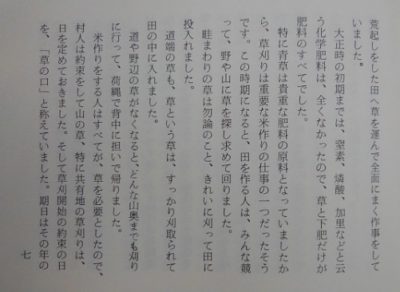
一文
大正の初期までは、窒素、リン酸、カリなどと云う化学肥料は、全くなかったので、草と下肥だけが肥料のすべてでした。
特に青草は貴重な肥料の原料となっていましたから、草刈りは重要なコメ作りの仕事の一つだったそうです。この時期になると田を作る人は、みんな競って、野や山に草を探し求めて回りました。畔の周りの草はもちろんのこと、きれいに刈って田に投入しました。道端の草や野辺の草がなくなると、どんな山奥までも刈に行って、荷縄で背中に担いで帰りました。
コメづくりをする人すべてが草を必要としたので、村人は約束をして山の草、特に共有地の草は、日を定めておきました。
草刈開始の約束の日を「草の口」と称えていました。
田の草と下肥で今年のお米の出来は決まりました。大正初期には、マメ粕と魚粕が牛車で運ばれて来たそうです。
田の草取り唄
壱 高い山から 谷底見れば 笹が見えたり かくれたり
弐 ナスビなれなれ キュウリはさがれ うりは てんころさと 寝てござる
三 親の意見と ナスビの花は 手に一つも あだはない
四 あの子 良い子じゃ ぼたもち顔じゃ きな粉つけたら まだよかろ
五 好いたお方と 田の草取れば こちらの間から手を握る
農村の農作業をしている風景が目に映ります。
大変な労働をしている農家の中で、
人の関わりがなんだか「ほっこり」しますね(^^♪
にんまり、してしまいました。
郷里
大正初期まで本当にきれいな景観が保たれ、雑草と人糞等を合理的に農業が営まれて、環境破壊、酸性化、獣害、プラごみ問題すべて解決。
暮らしにみんなが携わっていたんですね。
「もっと大事に土づくりをしなさい」と先人に、ハコベに、ホトケノザに教えて頂きました。

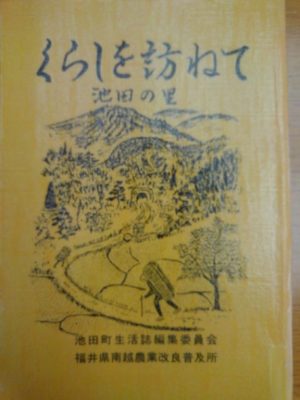



コメント