大根は比較的簡単な野菜と言われています。また秋作は美味しい大根がとれますし、田舎の畑では絶対と言っていいほど大根を作っていますよね。
そこで今回は大根がうまく育たない理由と解説します。
そもそも大根栽培で初歩的なミスを犯していないでしょうか?
ご確認ください。それについてはコチラ↓をご覧ください。


大根の土づくり【準備と排水対策】
ダイコン畑の排水が良い事が、第一。
大根は排水良い畑で作る
穴を掘って水がしみだす(地下水位が高い)と大根の根が嫌がってそれ以上伸びません。
大根の産地には砂地で栽培している場合が多いのもその理由です。
そして「大根が長くならない」「又根になるのはどうして」の原因は、排水不良がほとんどです。
よく「又根の原因は、石や肥料に当たった」という事を耳にします。しかし、それはほんの一部で、それだけの理由ではありません。
そうなると次第に葉が黄色くなり、いつまでたっても生育が悪く大きな大根が取れません。
畝を立てることも考えましょう。
排水対策ができている畑とそうでない畑では生育が大きく変わります。
大根の畑は深く耕す。畝を立てる
土が少なく浅い場合は、畝を立て、土の量を確保する。
細かく言えば最低20㎝は土を深く耕す必要があります。
青首大根葉は一般的に抽根性(地面より上に伸びる)があります。しかし、地面の下にも伸びます。
大根の理想は40㎝の根長が必要です。そうなるとその半分の20㎝は地面の下に伸びます。その半分は地上です。
地上部が長くなればなるほど、葉の重量で曲がります。また、大根の先端部の根はそれ以上に地中に潜ります。
深さが無い場合は、畝を立てると良いですね。
砂地好み、固く締まらない。細かい土がきれいな大根になります。
たい肥で土づくりは問題あり
未熟なたい肥を入れて栽培すると大根の肌を汚くします。
たい肥は毎年施したほうが良いですが、大根の作付けの直前に播くと大根の肌が汚れ易いので前作の時にしましょう。
例えば
春にたい肥を施し、「瓜類、かぼちゃ、メロン、スイカ、ジャガイモ等」を作った後です。その後作に大根を作付けします。
因みに大根までなにも作付けしない場合は、太陽熱消毒しておくと、病害虫や雑草が生えにくくなります。
肥料はなんでも良い。
肥料はなんでもいいと思います。ただし大根の収穫までの日数は約60日です。その期間は最低必要。
有機質肥料中心の場合は、若干肥料の効き目が遅いので大根が採れるまで日数がかかります。
やや多めで全面に有機肥料と化成肥料を混ぜて元肥中心で行きましょう。
有機質肥料であれば、1アール(10m×10m)10㎏は必要。
有機質肥料は効き目が遅い為、事前によくなじませておく必要があります(2週間程度)。
大根は収穫までは60日程度、秋は寒いから追肥の効果が弱いです。
大根の間引きは2回するのが理想。
大根の間引きは重要な作業です。
もし大根の間引きをしなかった場合どうなるでしょう。
↓この画像は大根の間引きをしないで栽培したものです。
中央に大根が3本生えています。種をまいたのは同じ日です。生育に大きな違いがみられますよね。

するとこのようなばらつきが発生しました。どの大根も決して良いとは言えません。
このように大根が不ぞろいになった理由は、「抽根と競合」
植物は光を求めて生育します。その時に大根同士が競争し、上に上に伸びます。
「特に青首大根では抽根性が顕著です。
伸びれなかった大根は光あたりが悪くなり青○は大きく太る事ができません。逆に緑〇は大きくなりすぎて、曲がりが発生しました。
また、土の中でも同じように大根の根でも肥料の奪いあいが起こります。これを「競合」と言います。
株間をあけることで回避できるのですが、肥大が進み過ぎて、曲がり・奇根やス入りの原因となります。
大根の間引きの方法
間引きは一度に行わず、2回に分けて行います。
1回目は本葉1~2枚目のときに、子葉の形が悪い個体や、虫に食われたものを引き抜きます。2本残して他の株を取ります。
子葉が奇形のもの・間延びしているものは大根になっても形が悪いです。
1回目の株間は本葉2~3枚程度で15㎝位にします。
2回目は本葉4~5枚目のときに、1本になるように間引きます。
奇根になっている大根の見分け方
本葉4~5枚の頃から奇根になっている物があります。
その見分け方ですが緑が濃く茎が極端に太いものは股割れ、奇根に、茎が黒いものは病気になっている可能性があるので抜きましょう。
なぜ緑が濃くなるかというと、根の方に光合成で作られた養分がいかない。すでに奇根になっているので根に養分が必要ない為、葉に養分が流れます。
その為、葉が濃く見えるのです。
また、生育の悪いものや、虫に食われたもの、斜めに生えている個体も間引きます。この時の大根の株間は25㎝位が良い。
ただ、そこまで大根をしっかり見極めるなんて慣れるまで難しいですから、感覚で大丈夫、2本のうちどちらが揃っているかです。
早く太い大根にしたい?細くながい大根にしたい?決めるのは間引き
つまり、間引きで大根の生育を早くしたり、遅くしたり決めることができます。
例えば、
太く早く収穫したいなら、間引き2回、最終的に株間30㎝以上に広げる。
細く長い期間収穫したいなら、間引き1回、株間20㎝位に狭くする。
光当たりと、肥料が他の大根に取られなければ早く大きくなります。

マルチでも同じです。間引きして採取的に1本にした場合は大きさがそろいます。生育が早く、肥料も効き目が良くて良いものが取れます。
一般的に、秋作では黒マルチを、春さきはまだ寒いので保温を兼ねて透明マルチ栽培することが多いです。
秋大根栽培の手順「中規模10アール以上の大作りしてみました」
種まき(播種)
耕起(粗おこし)→施肥→耕起(整地)→播種
大根のは種は簡単な播種機「クリーンシーダー」で種まきするととっても便利です。
大根発芽は3日でそろいます。3日して発芽がそろわなければ、もう生えません。まき直しします。
大根の大きさに合わせた穴に1~2粒ずつ等間隔に落としていきます。

大根蒔いたら絶対覆土しないといけません。
タネに日光があたると生えません(嫌光性)。種はちゃんと土に隠してくださいね。
間引き作業は手間なので何回もしません。規模が大きくなるとそこまで手が回らなくなるので1回までです。
株間は15㎝の1粒まき、大根専用の播種ロールを使います。
もう一つのポイントは播種した後の水やりです。雨がサッと降る位がちょうどよい。
日照りの場合は発芽までは、水やりをしっかりとしましょう。
大根の害虫対策
初期に防ぐ
また、初期の害虫被害が致命傷になるので、発芽後2週間程度はしっかり様子を見てあげてください。発芽後の2日程で全滅ってことも良くあります。
毎年出るなら、きっちり防ぎましょう。去年出来たから今年は去年通りで大丈夫って思っていませんか?それは大間違いです。害虫も同じ事思ってます。「去年ここにいい大根あったから今年はもっと大根かじれるよ」ってね。
〇農薬を使った防除方法
大根の害虫はダイコンサルハムシなどハムシの被害が大きい。そこで農薬を使います。
ダイアジノン粒、フォース粒剤などの農薬を10アール当たり3~6㎏、タネまき前に散布しておきます。
〇農薬を使わない防除方法
これについての記事は

〇害虫の発生時期をずらす方法
秋作大根の播種時期(北陸地方)は8月下旬ではまだまだ残暑が厳しいですね。9月中旬では少し遅い。
早く撒けば病害の恐れがある。遅くまけば病害虫は減る
これは、秋作の大根の生育にとって一番良いのが、夏が過ぎ、涼しくなった8月下旬ごろ。しかし、一番害虫や病気にさらされやすい時期です。
ハムシや軟腐病を避けるために、もう少し種まきの時期を遅らせ、病害虫の活動がおさまる頃を見計らって蒔く方法です。
しかし、あまり遅く蒔くと生育が遅れ、寒くて収穫できない状況になります。
特に害虫「ハムシ」は初期の被害が甚大で、初期の防除がとても大事。大根が大きくなれば、少々ついても、大根の生育が早いので問題ありません。
私は9月初旬から中旬と決めていますが、皆さんの地域のベテランさんが撒く日を聞きましょう。聞いて怒る人はいないです。喜んで話してくれると思いますよ。 ( ´∀` )
大根の生育初期

播種5日後↑大根の双葉が展開しました。株間は15㎝の1粒まきです。
害虫が多発する畑では、もう、この時点で害虫が卵を産み付けています。

播種20日後↑大根の本葉が4~5枚展開しました。
ここまで大きくなると害虫の被害が少なくなります。秋まきはどんどん寒くなり、大根の生育も良くなる為、少々かじられても気にならない。
大根の間を起こします(中耕1回目)
条間70㎝取ってます。1~2粒まき・株間は15㎝です。20日後、本葉4枚程度で畝間を管理機で起こします。
小さな雑草を打ち込み、土を柔らかくします。
大根の生育中期(中耕2回目)

中耕・培土をします。2回目の条間を耕します。中耕管理機で土寄せしています。もっと大規模になるとトラクターのような乗用もあります。
大根の追肥
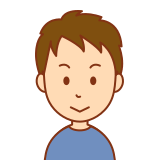
大根の葉が薄い・黄色いけど、肥料がたりない。
もし大根の葉の色が黄緑ががかっていたら肥料、特に窒素肥料が足らないです。
その場合、化成肥料を蒔きます。特に、窒素が多い肥料を選ぶとよく効きます。
化学肥料と有機肥料では葉の色の出方が全く違いますから有機肥料100%で大根栽培するのであれば、最初の肥料が沢山必要になります。
この作業の前に追肥として全体にまいてから作業すると土と肥料がなじんで、効き目が促されます。
追肥は効き目が穏やかなので。ここまで来たら有機質肥料での追肥はしません。見守るだけ。
大根の収穫(播種後60日前後)
収穫期に近づくと大根の見た目もちょと変わってきます。
今まで立っていた葉の外葉が扇を広げたように垂れてきます。
傘のように均等に大きく広がっていた葉が、少しばらけたように見えます。
また、大根が地面からせり出してきます。下の画像見てください。

大根に土がついていますよね。これサルが引っぬいた訳ではないです。( ´∀` )
これが青首大根の特徴である「抽根性」です。
大根が勝手にせりあがって来たんですよ。「もう、ぬいて~」

せり上がりが10㎝位あるでしょうか。しかも短期間で急激に成長していきます!これが収穫適期です。
もともと土が浅かったのですが、それでも30㎝は地面に根をおろしています。


早朝、みんなで一斉に収穫です。大根がそろってすべて収穫できました。ちょっと曲がりましたが、漬物なら問題なし。
まとめ
①種まきと間引きは収穫したい大根によって、間引きのやり方をを変えます。
太く大きい大根をできるだけ早く収穫したいなら、できるだけ間引きをこまめに広く株間を取る。長い間、細く長い大根が欲しいなら間引きを少なく、間引き間隔で長く収穫しよう。
②害虫は、いつもあなたの畑を見ています。
人間「今年良いもの採れたから来年もここでちょっと早く沢山やってみよう。」虫「今年ここにこんないい大根がたくさんあったね。来年はもっとみんなで食べちゃおう。」きちっと害虫対策をしましょう。害虫が発生してからでは手遅れになることもあります。
③大根は高温・乾燥が苦手です。
播種のタイミングがすべての作業に影響します。なので地域に見合った時期が絶対です。早撒きは私はおススメしません。失敗の原因はここにあると思います。また、大根の収穫適期はあっという間にやってきます。収穫適期を逃すと芯いり原因になることもありますので注意してください。
④丁寧に深く耕す。土が少なく浅い場合は、畝を立て、土の量を確保する。
大根の根の障害
又根
未熟たい肥や肥料などのある所に、根が伸びてきた場合、根の先端が痛んでしまったことによることで起こります。したがって、大根の肥料はなるべく早く土になじませておく、たい肥は前作の時にいれ、大根作には使わない方がいいと思います。
ス入り
切ってみると中がスカスカのスポンジのようになっていること。瑞々しい感じではなく白く濁って見えます。
根の肥大が急激に起こるような場合です。株間を大きく取り過ぎてしまった場合、どんどん成長が進み過ぎています。
また肥料と気温に影響されてこの症状が起こります。なので早撒きしないようにお願いします。
皆さんの地域に合ったまき時です。私の地域だと9月入ってからですね

上の縦割りした大根見てください。先の方が黒い筋が入っているのがわかりますか?

では、青首のところはどうでしょう。切ってみるとこんな感じで白くなっているのがおわかりだと思います。こうなってしまうとほとんどの大根も同じ症状です。全て無駄になってしまいますね。
裂根
大根の根に縦にひびが入る現象です。これは中と外の根の成長バランスが崩れて起こるので株間が広い所に多く発生します。少し株間狭くしてみてください。
網入り
根の表皮に網目があるように見えます。これを網入りと言います繊維が固いです。高温・乾燥状態で起こるので気を付けましょう。
ps あと大根引きには腰痛にご注意。


コメント