畑や田んぼの土づくりをしましょう。って何!?
野菜作りの本や雑誌ではよく描いてあります。「まず土づくりをしましょう。」「物理性・化学性・排水性・保水性・生物多様性を改善しましょう」とはどういう事でしょう?
別けわからない。私もそう思います。
この記事では、土作りについて説明しています。「畑の土づくり」とは漠然として良く分からないのではないでしょうか。
色々な考え方があるのですが、ここでは、土づくりの考え方とたい肥の2つに絞って解説しています。
畑の物は畑に、山の物は山に返す。
1つは、ある農家の方が「木は木に返せ、草は草に返す」という法則があるといいます。木などゆっくり育つ作物には、ゆっくり分解する有機物が良いという事です。さらに「すべての生き物は存在する意味がある」と言うことです。宗教的・精神的な発想に見えますね。
例えば木を分解するキノコ、落ち葉をかじるヤスデ、ゆっくり落ち葉を分解ミミズ、葉に残ったタンパクや糖を分解するバクテリア、すごく多様な食物連鎖によって山の土が作られているんです。畑も同様です。生物の住みかを変えないようにする。つまり生き物の生態(食物連鎖)を壊さないことが重要と言っています。
ただし、ただ単に畑の野菜くず・残さは畑に戻せばよいのでしょうか?いいえそう単純ではありません。
生き物の生態を考えた使い方なのです。
江戸時代の農業書『百姓伝記』にはこのような一文あります。
「藁は畠のこやしに良く効き、万物草をいのこやしとしれ。麦畑の根こえに用いる、畑やわらぎ、夏作毛までよくできるなり。夏作毛・秋作毛までよくできるなり。
夏作毛・秋作毛のこやしにすべからす。諸虫多くわくものなり。」
これは、直訳すると「ワラは畑の肥料によくきき、全ての植物体の生長の肥料となる。麦畑の元肥に使用すると、畑はふかふかになって、その後の夏の野菜の生長が良い。
夏の作物の残さを秋の作物の肥料に使ってはいけない。様々な害虫の発生源となる。」
つまり、現代農業で言えば水稲後のワラは分解し易く、窒素もあるので麦作との田畑輪換として有効であり、収穫した後の麦の繊維は分解しにくい為、畑の排水性や保水性が良くなる。
更に、夏の植物残さには、病害や害虫の卵・雑草などがいるので、そのまま畑に入れないでたい肥化して入れる。
「畑に作るものもの品々の草がら葉、田の肥やしとなる。冬のうちに塊田やくれ田にふり入れ、くさらすべし」
これは、畑で作る野菜のくず・雑草は、田んぼの肥料となる。冬のうちに耕した田や乾燥した田んぼに入れて腐らすとよい。
つまり、田んぼの藁は畑の肥料になり、畑の野菜くずは田んぼの稲わらの分解に使う。秋に野菜くずを入れて耕起(秋起こし)することでワラの分解を早め、春の土づくりの準備が整います。
私のふるさと池田町では、田んぼの土のことをアマ(天)と呼びます。
突然ですが、世界で最高の土はどこにあるんでしょう?
答えは旧ソ連「チェルノブイリ原発事故」があったチェルノーゼムです。中学の勉強で聞いたことがあると思いますし世界の穀倉と呼ばれ、土の皇帝――。そう呼ばれてきた土です。「チェルノーゼム(黒い土)」。
土壌の養分が豊富でバランスがよく、作物の栽培に非常に適した性質の土。アメリカのプレーリー、アルゼンチンのパンパなどにも分布するタイプの土で、世界で最も肥沃な土として地理の授業などでもおなじみの存在となっています。
日本の黒ボク土よりもっと黒い土の層で覆われています。ここは寒いので草原です。冬には雪に覆われます。豊富な枯れ葉や草が微生物によってゆっくり分解された状態(腐植)や養分が多く含まれているからだそうです。その地域の農家さんの肥料の認識=窒素Only、っていう話も聞きました。
私の郷里の図書館に「暮らしを訪ねて」という農作業の歴史書がありました。
昔田んぼ作業に「草の口」という日がありました。
これは、水田に入れる肥料がまだなかった時代です。水田に入れる肥料の代わりに、山や畔刈り取った草を水田に入れて肥料にしたそうです。
青草は、現代でいう「肥料であり腐植」に当たります。草を入れることによって水田に有機物と窒素肥料を入れることができます。
しかし春先の柔らかい草はすべての水田に入れるほど沢山はありません。なので、「草の口」という日を区切って、一斉に百姓の皆さんは草刈をして水田に入れたそうです。
「土づくり」というものを非常に大切に守り「アマ」と呼び「天」と書きました。今ではアマと呼ぶ人も少なくなりました。
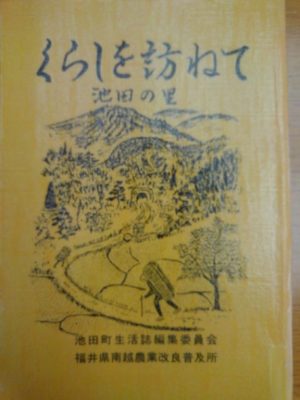
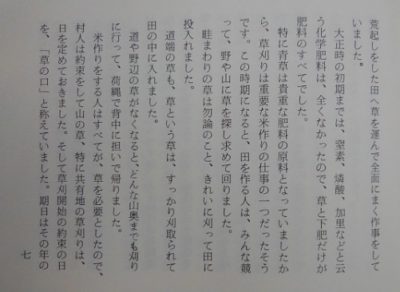
漁師さんの解禁日みたいな感じ。たぶん当時は、山も畔も田んぼも草刈してあり今以上にとてもきれいな水田風景だったと想像します。
土づくりとは、土に腐植を増やし、通気性や排水性を整え、保肥力を保つ事ですの意味が少しわかったような気がします。
安く、簡単に土づくりする方法?
それはたい肥を入れる事になるのですが、
簡単にあるもので作るならコチラ。皆さんご存じだと思います。生ごみ処理機コンポスト。
つまり、たい肥を作って畑に入れる事です。
日本では、チェルノブイリのような土はありません。人間の手「草の口」で作らなければいけないのです。

コンポストたい肥の作り方
コンポスト容器の底が10~20cm程度土に埋まるように設置します。
コンポスト容器の中に、腐葉土・落ち葉・もみ殻・ぬか・古土を入れよく混ぜる。軽く水をかけます。
これで準備が整いました。そして、野菜残さ・生ごみを投入します。
できれば、風乾した生ごみ(1~2kg)を入れ、その都度よく混ぜ合わせます。生ごみのほかに落ち葉や雑草・米ぬかなど。
偶にはフタを開け、通気を良くしましょう。また、スコップなどで中を掘り返して空気を入れてください。(好気性醗酵させます)
醗酵してくると暖かくなり、攪拌するたびに水蒸気が発生します。腐敗すると悪臭が出ます。
私の町ではこんな感じ。手作りで十分!!使い古したマルチと木枠で作っって、巻きやすいように畑の中!

ここだけの話です。1年以上コンポストを置いてあった真下の土は、最高の土。
チェルノーゼムにも負けません。
無肥料無農薬で作れます。野菜がびっくりする位、きれいでそれでいて美味しいです。
マジです!是非コンポストがご家庭にございましたら試してみてください。
土だけで十分。ただ面積がコンポスト分の所なので小さいのが残念!!
田舎流のたい肥の作り方をご紹介します。
材料
・畑で収穫した野菜の残サ(トマトの茎や大根の葉、スイカやミカンの皮やくずイモ・雑草までなんでも)
・もみ殻(通気性をよくする)・落ち葉
・たい肥(完熟牛糞たい肥でもOK)
・畑の土(どこでもよいが野菜が良く作れる土)
細かいことは言いません。畑の野菜の収穫した残サならなんでも有るもので十分。ただし、塩や調味料やサラダ油等はだめです。口にするものは何でもではありません。
作り方
これらをミルフィーユのように層になるように入れていく。かき混ぜないで薄い層を何層もです。これで完成です。本来なら攪拌して好気性醗酵を促進させた方が早くできるのですが、長く放置して、たい肥化させていきます。
嫌気性醗酵によって匂いが出てきますので気になるようなら、フタをしたり、最後に土を多めにかけたり、近所迷惑のない畑で。
使用方法
半年以上寝かせることが重要。私はこのような場所を2か所作って交互に使います。最初の匂いは湯気とともに強烈です。しかし、最初だけですが近所迷惑にならないところで。
使い方は、下からたい肥を使う事です。上の方はたい肥化していませんのでまだ使いません。
効果
①土を軟らかくします(土の団粒効果を高め、水はけが良くなります)。
②地力が高まり、肥料が長持ちします。また、水持ちもよくなります。
③土に力があるので肥料をやりすぎても野菜が蔓ぼけしにくくなります。
④野菜自身の食味が上がります。
⑤微生物・昆虫が増えます。
未熟堆肥を畑に入れるのは危険です✖。
①未熟堆肥の中にある牧草種子が発芽し、見たこともないような草が勢いよく生えてきます。
②堆肥が未熟であるとまだ発酵しています。発酵するときにガスが発生し、植物を傷めます。
③微生物が有機物を分解するときに土に含まれる窒素を吸収し肥料不足に陥ります。
④一部の病原菌を増やしてしまうために、病気にかかりやすくなります。
未熟堆肥は、ねかしておき(半年放置)、そのまま畑に入れないでおきましょう。
土を整えた状態にします。(酸度矯正とph)
これはあまり深く考えなくていいです。野菜は日本原産のものが少なく、世界中から日本にやってきました。
そこで土の相性を調整するものです。そうすることで、後々、肥料の効き目が違ってきます。
日本の土壌はphにすると5.0~6ぐらいの酸性土壌、多くの野菜が好きなphは6.0~7.0前後です。若干相性がよくありません。
中性に近い弱酸性なんです。変な言い方ですね。ph6.5ならほとんどの野菜が作れます。
少しアルカリ性の資材を入れて調整してあげます。
石灰の使い方についてはほうれん草の育て方 失敗の原因は土づくり⁈【石灰のやり方】
資材は、よく校庭などに白線が引いてありますよね。あの白い粉はアルカリ性なんです。消石灰って聞いたことありますよね。
欲を言えばホタテやカキ殻などを砕いた動物質の有機石灰がいいですね。アルカリ成分もきつくありませんし、海のミネラルたっぷりです。
目安です。(入れすぎはだめです。病害を助長します、肥料の効き目が変わってきます。普通に野菜が採れるなら入れない方がいいかもしれません。
あげることは簡単でも下げることは非常に難しいです。最悪、硫黄とか使います。)
| 畑の状態 | (有機石灰) |
| 有機物に富んだ黒い土 | 220g~300g |
| 粘土質・普通畑 | 180g~220g |
| 砂地 | 100g~150g |



コメント